
Name名無し22/08/24(水)14:51:56 IP:49.98.*(spmode.ne.jp)No.541765そうだねx2
10月26日頃消えます 本日は「愛酒の日」だそう
というわけでアルコールと軍隊のスレ 削除された記事が1件あります.見る
…No.541766+  慰安品?医薬品?それとも燃料? サケと軍隊について語って! |
| …No.541770+>慰安品?医薬品?それとも燃料? >サケと軍隊について語って! それもう潰れたんですよ 世知辛い世の中だが、若い兵隊さんも酒呑むのかね? |
| …No.541772そうだねx1昨日DVDでみた映画でソ連の捕虜になった兵士が地雷原歩かされていて 「地雷処理部隊のウォッカの消費量が一番多い」と言われていた |
| …No.541779そうだねx1艦艇内禁酒が通常の米海軍での「スチールビーチピクニック」は楽しいんだろうね。 海自でも特別な場合(長期航海や歓迎行事)に艦隊司令の許可があれば飲酒可能だとか。 |
| …No.541780そうだねx1朝鮮戦争やベト戦時の米軍では、バドワイザーやOD色缶のビールが前線に支給されていたけど常温で飲んでいたのかね? |
| …No.541788そうだねx1亡父はジャワで一〇〇式重爆を操縦していたが 定時哨戒飛行は哨戒が目的なのか夕食用のビールを冷やすのが目的なのか判らぬ有様だったとか |
| …No.541789+飛行機にビールを載せて冷やすのは古今東西どこの軍隊でもやるものなんだなぁ |
…No.541792+  海軍時代から納品 |
…No.541793そうだねx1  最近、巷では若者のビール摂取量が減ったと聞くが、 自衛隊でも飲酒量は減ってたりするんだろうか? |
| …No.541798+>海軍時代から納品 呉の所属艦だと下士官兵用が千福で将校用は西条の賀茂鶴だったとか聞いたな |
| …No.541805+>最近、巷では若者のビール摂取量が減ったと聞くが、 >自衛隊でも飲酒量は減ってたりするんだろうか? 昭和、平成入隊の若い営内隊員にとっては週末に飲み会、コンパ、キャバクラ、クラブ通いが生き甲斐でストレス発散 何かしらの規制で「週末外出禁止」を受けることは死刑宣告に近いペナルティだった 最近聞く話が、今の若い営内隊員にペナルティで外出禁止をくらわしても「あー、部屋でネットするから別にいいです」となるらしい 酒飲めなくても構わない、飲み遊び興味ない、外出しなくていい、と時代は変わったとか その影響で海自は最近になって「護衛艦にWi-Fi設置します」と宣伝してたよね |
…No.541807そうだねx3  戦艦「日向」の乗組員だった丹羽徳蔵さんという方の手記に、同艦の「酒保長」 を命じられ、前任者から引継ぎを受ける話が出てくるんですが、曰く「30区の倉庫には、明細書によると、アサヒビール3960本165箱、サッポロ黒ビール2328本97箱、加茂鶴336本28箱、白鹿1524本127箱があることになっており、31区の倉庫にはキリンビール7800本325箱、日本盛1044本87箱、月桂冠1524本127箱、菊正宗684本57箱、三ツ矢サイダー2016本84箱というように膨大な数量で、全部いちいち当る訳にはいかない。そこでダース入箱が何箱で何本というように、箱数で引継ぎが始まった」…そうなんですが、「『箱の中の本数は当たった事はありますか?』と(略)念のため尋ねた」 |
…No.541808そうだねx3  …ところ、 「『分かっているので当たった事はない』との返事であった」…ため、念のためいくつか見当をつけた箱を降ろして中身を改めたところ、中味のない瓶に麦藁の覆いだけ戻して誤魔化したものの混じった箱が、続々と出て来てしまったんだそうで要はIJNお馴染みのギンバイ被害であり、結局改めての調査の結果、「アサヒビールが23本、サッポロ黒ビールが5本、キリンビール3本、酒2本」の不足が判明、前任者の方は気の毒にも顔を青くされていたそうなんですが、幸いにも厳重注意のみ、不足数は破損処理ということでケリがついたそうですいつもは毀損簿の理由にうるさい掌経理長も、この時ばかりは無条件で判子を押してくれ、かえって「御苦労であった」と労われたそうなんですが、それにしても「日向」の酒保の種類の豊富さ、左党にはさぞかし喜ばれていたんではないですかしら…w |
| …No.541823+駆逐艦雪風の戦記で、海戦直前まで乗組員がビール飲んでる話があったなあ |
| …No.541825そうだねx1海軍なのにウイスキーがないとはこれ如何に? |
| …No.541831+>昭和、平成入隊の若い営内隊員にとっては週末に飲み会、コンパ、キャバクラ、クラブ通いが生き甲斐でストレス発散 >何かしらの規制で「週末外出禁止」を受けることは死刑宣告に近いペナルティだった マジでそう。曹候補士が無くなる前(前世紀の)補士の1士とか士長が(何かと理由を付けて)出て。そのせいで一般の1士や士長が出られなくなった。 |
| …No.541833そうだねx1課業終了後、帰る支度をしていたら営内士長君がおずおずとバインダーを持って入ってくる。 「もう帰るので明日にしてくれ。」 「あ、わかりました。」と言って帰ろうとする。 ん・・・と気になって「見せてみろと」いって取り上げると外出申請。 「バカタレ、こういうのは土下座してでももらいに来るものだろうが。」と言ってハンコを押す小隊長。 >海自は最近になって「護衛艦にWi-Fi設置します」と宣伝してたよね 空自も離島のサイトでWi-fiを整備しようとしていたような。 |
…No.541838そうだねx3 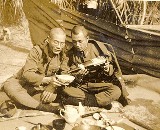 大戦中、我がIJAでは中国大陸で戦う将兵さんたちの為に、日本国内から大量の 日本酒を送っていたそーなんですが、何せ調達量が多量で現地で長期保管されることから、保管中乳酸菌の混入で変質したり(「火落ち」とよばれる状態ですね)、樽の木臭がついたり変色して美味しく頂けない状態になることが屡々であったんだそうでそんなわけで、例えば昭和15年8月に支那派遣軍が、大本営に対し変質した日本酒を「手入れ」する用品の追送を依頼していたりするんですが、内訳は「清澄剤光(沢田化学研究所製)15キログラム、玉渋(柿渋)12斗、醸造用炭酸カリウム(※酸っぱくなったオサケを脱酸するのに使うそう)80ポンド、乳酸(醸造用)50ポンド、サルチル酸(日本酒防腐用)30ポンド、グルタミンソーダ(日本酒調味用)30キログラム、琥珀酸(同)15キログラム、石綿15ポンド」 |
…No.541839そうだねx3  「大桶(20石入)4個、王冠(1升瓶用)3万組、輪竹(20石樽修理用、現地産の竹は 脆くて使用不可)6本文」…というものであったそうですこれで現地に貯蔵されている日本酒83万1千リットル中、約5万4千リットル(約6.5%)が変質するものと見込んでの調達量になるんだそうなんですが、当時陸軍嘱託で日本酒の「手入れ」に従事されていた坂本隆之助さんという方の回想によると「陸軍が日本酒の手入れを行った理由は、唯一無二の慰安が酒しかないためである。特に満州の奥地地方の場合、故郷を遠く離れ、零下30度まで下がる極寒の荒野での寂しい生活である」 |
…No.541840そうだねx4  「新京、奉天、哈爾浜の都会を除いて、兵舎のほとんどが支那家屋であり、天 井は高粱殻を泥で塗って防寒しただけに過ぎない。このような劣悪な環境で慰安など何もなく、映画や芝居も見られない状況では、酒が飲めるかどうかが非常に重要になる。そのため、変質した酒でも飲めるようにする必要があった」…とのこと最前線の兵隊さん達の最良の友だった、と言うことみたいなんですが、氏の記録によると当時前線に届けられていた銘柄は「初鶯(長野県)」「富久娘(灘)」「金露(魚崎)」「末廣(福島県)」「爛漫(秋田県)」「忠勇(灘)」「真澄(長野県)」「菊正宗(灘)」「櫻正宗(灘)」の他に、朝鮮や満州の醸造所によるものなどもちろん、1個所でコレだけ多数の種類を選べたワケではないんでしょうけれど、「陸軍御用達」の銘柄も、かなりバラエティ豊かであったようですねえ…w |
| …No.541854そうだねx2日本酒を運んで苦労して手入れして供給するのであれば 焼酎でも送ればその手間もいらないんでそのほうがよかったんじゃ・・・ あと現地調達しなかったんだろうか? 中国なら白酒とかいくらでも手にはいりそうだけど 当時の日本)人の口には合わないだろうけども まあ飲兵衛なんて多少口に合わなくとも酒があればのんじゃうしねぇ(俺がそうだが) |
| …No.541868そうだねx1南方任務の艦艇の方が保存環境は厳しいと思うけど寒冷な大陸でも日本酒は酸化しやすいのか |
…No.541871そうだねx5 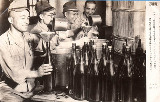 昭和16年8月に中国の第11軍貨物廠長に命じられた紺田修一さんという方は、現 地漢口で日本酒造りを始めておられるんですが、きっかけは内地からの追送品の酒樽が、しばしば途中で盗み飲みされる事態が屡々であったことだそうですw良いオサケ造りは良い水から…ということで、当時市内で空き家となっていた6階建てのデパートを改造、「雨樋2000m、4斗樽20個、木炭40俵」を使用する大規模な濾過施設を建設、延々6階から1階まで流れ落ちながら濾過された水は、「内地の井戸水を飲むような味」に仕上がったとのことそこで改めて岡山県から民間の杜氏さんら約10名を招き、製酒用機具として、直径約2mの樽50樽と4斗樽400樽分の材料および何万本分の1升瓶も用意されて、本格的に製造が始められたそうなんですが、数か月後に出来上がった酒の品質は「内地のものに匹敵する良好なもの」であったんですとか |
…No.541872そうだねx6  特級酒に相当するものは「悠久」1級酒相当が「大陸」と銘名され、それぞれ 将校用と兵用に区分されたそうなんですが、「悠久」を試飲した当時の軍司令官横山勇中将などは、1〜2杯のみ「日本でも滅多にこんなうまい酒は飲めない。特級酒賀茂鶴の味によく似ている」…と非常に悦び、且つ激賞したそうなんですが、実際内地から召集された酒造用員の方々は元々「賀茂鶴」の蔵元の方々であったとのことですので、中将の評価も妥当かつ的確なものであったようですその後これをきっかけに広まった大陸現地の酒造能力は次第に拡充され、内地からの追送がなくても、余力を持って民需にも応じられるほどになり、終戦まで生産も続けられたそうなんですが、「現地自活」が見事に成功した例の一つというというわけみたいですなあ |
| …No.541878そうだねx2兵士には喜ばれても結局は嗜好品だからね 限られた輸送力を割く位なら現地生産した方が合理的ではあるな |
| …No.541882そうだねx4>No.541872 面白い話ありがとうございます |
| …No.541888そうだねx3お米を原料にするわけですし、考えたら現地生産も余裕のある所でしかできないですよね… 比較的戦況の良かった中国大陸ならではの話だったのかも |
| …No.541890そうだねx1日本酒の現地生産は今や色んなとこでやってるけど 当時でもやってたんだねぇ |
| …No.541891そうだねx1中国酒も美味いけど今と違って内地の娯楽に触れる機会なんてないから せめて嗜好品だけでもという欲求は強かったんだろうな |
…No.541897そうだねx5  千島列島に転回していた日本陸軍の部隊では、海岸で砂と海水を被ってしまい食 用に適さなくなってしまったおコメでおサケを造っていたそうです麴菌の代わりに、薬の「ワカモト」に含まれる酵母を使って、ドラム缶で「醸造」したそうなんですが、兵隊さんたちの生活の知恵というか、飲兵衛の執念恐るべしというところでしょかね因みに日本酒製造は南国タイなどでも行われていたそうなんですが、タイ駐屯軍の経理将校だった三宅一郎さんによると「バンコク貨物廠は、タイ米を使用して(略)台湾から杜氏を迎え、バンコク競馬場内に開設した貨物廠内で、見事に日本酒醸造に成功した。気候が暑過ぎるため、酸味が多少あったが、中村軍司令官はこの酒に『大義泉』と銘名し、日泰間の公式パーティ(略)にも必ず(略)出して、仏の国の母なる川、『メナム』の水とタイ米を使って作った日本酒(略)と紹介され、親善に大きな役割を果たした」 |
…No.541898そうだねx5  …そうなんですが、一方では 「貨物廠は補給量を節減するために濃縮し、濃厚酒として倍にうすめて飲むことと注釈をつけたが、部隊では『特急酒』と称し、うすめないでそのまま飲み、酔いの回りが特急と喜ばれた」…とのことで、味は二の次、酔えるのが一番!という方々にもウケがよろしかったようです因みに更に南方のニューギニアに展開第18軍の補給を担当する第27野戦貨物廠でも、「醸造班」の方々が上陸以来「現地資源を以てする醸造法の研究に精励」しておられたそうなんですが、昭和19年以降、いよいよ連合軍側の反攻が本格化して、日本軍が密林内に追い込まれて補給が途絶してしまった状況下でも、なお「廃米を回収して此より清酒を醸造して各部隊に補給し、志気の振作に資」していたんですとか |
…No.541899そうだねx5  そしていよいよ廃米も尽きると、コメの代わりに現地将兵さん達の主食になってい たサゴ椰子でんぷんの搾りかすや、食用不適当の野生のコンニャクイモ(「電気芋」というやつでしょかね)を原料とする醸造法を研究、見事清酒や医療用アルコールの醸造に成功しているんだそうで敵に制空権を握られた下で、機材も乏しい中創意工夫を重ね「前人未踏の醸造法を発見」した醸造班に対し、第18軍司令官安達二十三さんより直々に賞詞が下されているそうなんですが、サゴ椰子やこんにゃくを原料としたという日本酒、例え酒造米使用の「本物」とはかけ離れた味であったとしても、孤立し厳しい生活を送る守備隊の将兵さん達にとっては、何よりの慰めであったんではないですかしら… |
| …No.541901+戦前なんて焼酎は一般化してなかったんじゃないかな 九州以外では芋が原料なら臭いと嫌がられたかもしれないし 蒸留過程が必要なら製造にもひと手間かかるから |
| …No.541903そうだねx2江戸時代に酒が多く造られたのって豊作の年に余った米を消費する面もあったと聞いたことがある 歴史を勉強してると飢饉の方に目が行きがちだけど、豊作のことはあまりわだいにならないよね |
| …No.541904+映画の捕虜収容所だと密造の蒸留酒が定番だけど 日本軍捕虜も何とか飲めそうなものを拵えていた話があるよね |
…No.541918そうだねx3 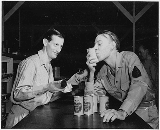 戦争末期にフィリピンで米軍の捕虜になった大岡昇平さんの「俘虜記」に、収容 所で米軍の使役に従事していた日本兵捕虜のある一隊の話が出てくるんですが、この隊はある日米軍兵士用のビールの梱包の山の積み替えを命じられたんだそうでそこでこのお宝の山を前にした捕虜の方々は一計を案じて、「新しい山の中央に縦穴が出来るように積んで行った。そして交替で穴の底に降りて、周囲の梱包を破り安全に鱈腹飲んだ」…そうなんですが、「こういう山は三つばかり出来上ったが、或る山で酔払って上がれない者が出たため、米兵に発見された。一隊は徹夜で積み直しを命ぜられた」…とのことで、折角のビール飲み放題作戦もおじゃんになってしまったとのこと |
…No.541919そうだねx4  因みに氏によれば、収容所内での飲酒はこうして米兵用のビールをくすねる他にも 「酒は甘味品として配給される乾葡萄にイーストを加えて醸造される。炊事場は無論この密造酒を切らしたことがないが、一般の俘虜も5ガロン入りの缶(ジープが後へ乗せている密閉装置のある扁平な缶である)を床下に埋める」「(※米軍側に摘発され)乾葡萄の配給は停止されたが、すると我々は外業先で盗み、或いは外業隊長が出先の係官に特に懇願して貰って来た。それも切れると、砂糖、蜜、ジャム、その他何からでも造った」…そうです「退屈した人間が、その欲望を遂げる手段を見つけるのを妨げることは出来ない」…というのが大岡氏の言なんですが、逆にある意味米軍の物資補給関係の豊かっぷりが、垣間見えるようなエピソードな気もしますですなあ |
| …No.541935そうだねx2戦国時代でも、雑兵足軽にあまり多く兵糧を先渡しすると酒にして飲んじゃう、なんて話があったみたいだね あまり旨いもんじゃなかったろうけど、もしかしたらそうやって酒を作る行為そのものか戦場でのストレス解消になったのかな? |
| …No.541936そうだねx2俺も趣味で酒造りするけどさ 自分で作ってみるとやっぱり市販の酒はよくできてると思うよ まあ長年酒造りをしてる酒造メーカーが作ったものと素人がその辺で手に入る材料で作ったもので同じような味ができるわけないよね 自分で作って味がバッチリ納得いく味にできたのはシードルくらいかなぁ・・・ まあ作る過程は確かに楽しい ・・・ア?イエチャントアルコールドスウ1%イカデツクッテマスヨ? |
| …No.541937+書き込みをした人によって削除されました |
…No.541938そうだねx1  https://sp.seiga.nicovideo.jp/seiga/#!/im5632913 酒が飲める酒が飲める酒が飲めるゾー |
…No.541939そうだねx1  https://sp.seiga.nicovideo.jp/seiga/#!/im10453812 酒が酒が飲めるゾ |
…No.541940そうだねx1  https://sp.seiga.nicovideo.jp/seiga/#!/im6867356 酒が飲めるゾー |
…No.541955そうだねx4  先述の今田さんと同じく、中国漢口でIJA第6方面軍経理部勤務だった佐々木正 壱さんという方の手記によると、昭和19年頃から内地からの補給も跡絶がちとなり、物資運搬用車両のガソリンに事欠くようになってしまったんだそうで補給の責任者として対策を迫られた佐々木さんですが、ある日「たまたま漢口城外に出張したとき、中国人の自動車がドラム缶に何か積んで漢口の方に行くを目撃して尋ねてみますと、これは支那酒なんですね。『漢口へ持っていって何にするんだ』と聞きますと『アルコールを作る』と申します。その製造場所を訪ね(略)出張から帰って直ぐ(略)アルコールを作っている現場を押さえたのです」「『これだ』と思いまして、経理部長にお願いして、とにかくアルコールを作ろうと」…思い立ったんですとか |
…No.541956そうだねx4  「兵器部だとかなんとかいっていられません。ちょうど兵隊の中に、そういう 技術者がおりまして、生産工程を全部スケッチしてくれましたので、製法の原理を理解しました」「漢口にてボーメ比重計を全部隊の数だけ買い、経理部部長通牒をもって、部隊の関係者を全部漢口に集め(略)アルコール製造の教育をしたわけです」「どうせ素人がやるわけですから、ごく単純に、原料の支那酒どれだけからアルコールがどれだけ採れるか、そのやり方はこうするのだ。それに使うボーメ計はこうであるといった資料を作って渡しました。これは部隊長から大変悦ばれました」「とにかく支那酒がどんどん部隊本部に集められますと、それでアルコールができて、車が動き、物資収集ができるわけで(略)おそらく兵器にも利用されたと思います」 |
…No.541957そうだねx4  「手前味噌ではありますが、中支の戦力は大体1年位伸びたのじゃないかぐら いに思っております」…というのが佐々木氏の自負なんですが、こうした現地自活の成功ぶりは現地総軍の注意も引いて、終戦間際には総軍側から漢口に技術者が送り込まれてきて、その指導の下に大規模なアルコール蒸留施設を建築する計画が立てられたそうですもっとも、佐々木氏らは例え大量の原料(酒)は集められてもその輸送自体がネックになる、いままでのようにやり方だけ教えて現地で必要量を製造させる方式の方が良い…と反対したそうなんですが、こちらは結局実現しないうちに終戦となってしまったとのこと昔読んだ本に、戦争末期の中国では酒を燃料に戦車が走った…なんて記述があった覚えがあるんですが、実際、燃料の一部にこうした現地製造のアルコールを使用した部隊があったりしたんですかしら… |
| …No.541961そうだねx2>あまり旨いもんじゃなかったろうけど 美味い不味いではなくて酔っぱらってストレス解消が主目的なんだと思う |
| …No.541963そうだねx2航空燃料用にアルコール生産は内地でもやってたね そして戦後は闇市で売られる怪しげな酒の原料に・・・ |
| …No.541978+>美味い不味いではなくて酔っぱらってストレス解消が主目的なんだと思う 酒では無いがベトナム戦争の時の合衆国海兵隊はそれはもう酷い荒れ様で、兵員を外に出してる間徹底的に宿舎を調べたらたくさん"お薬"が出てきたらしい |
| …No.541979そうだねx3電装品冷却用のエタノールを日常的に飲んでた軍隊もありましたね |
| …No.541980+ミグ25があればアルコール飲み放題だもんね 市販のウォッカより純度が高かったそうだけど何度くらいなのかな? |
…No.541984そうだねx3  日本陸軍航空隊の整備兵で、満州の第23飛行教育隊で勤務された田口頌二さ んという方の手記によると、「極寒の満州は、内地では考えられない訓練や勤務があった。朝、ピットへ行くと、97式戦闘機が滑走路の脇に並んでいる。ところが、どの機も発動機の上から地上まで天幕が掛けてある」「この天幕の中に2名の整備兵が入っており(略)エンジンを炭火で暖めている。エンジンの真下には、石油一斗缶があり、炭火が入っていた。零下の気温のため冷えたエンジンは、容易に点火しないのである。」「昔はこんなことはやっていなかったそうだが、燃料がガソリンから芋焼酎に代わったため、炭火暖房になったという」 |
…No.541985そうだねx4  「燃料補給の時揮発性のある芋焼酎は、ガソリンのにおいとは違って焼酎そ のもののにおいだから、酒好きな兵隊は『タマラン』といっていた」…そうなんですが、「ときにはないしょで飲む兵隊もあるのか、燃料の中にはオクタン価を高めるため4エチル鉛が入っており、これが毒であるから飲むことは禁止されていた」…とのこと実際には流石に「芋焼酎」そのものではなく精製アルコールであったはずですし、おそらくある程度ガソリンと混用しての使用だったのではとも思われるんですが、大戦後半に使用されたアルコール燃料が、現場でどんな風に扱われていたのか、伝わってくる感じではあります |
…No.541986そうだねx4  一方、こちらは内地の横須賀海軍航空隊で夜戦「月光」搭乗員だった黒鳥四朗さ んの回想記にも、アルコール燃料でのテスト飛行の話が出てくるんですが、曰く「水平飛行に移ってから、アルコールに変更した。機内にもともと染み付いたオイル臭を押しのけるように、しだいにアルコールの匂いが強まってくる。『速力が出ません。分隊士、これでは戦闘に使えないと思います』『すごい匂いだ。酔っ払うぞ。タンクを切り換えろ』酒をたしなまない私には、すてきな香りとは思いがたい。テストはこの一回だけで、匂いはともかく、速度を出せないのだから『空戦での使用には不向き」との結論を提出した」…とのこと性能が落ちるのも困りものですが、おサケ好きの搭乗員さんだと又別の意味で操縦に集中できなくて、困ったんではないですかしら…w |
| …No.541991+>ミグ25があればアルコール飲み放題だもんね >市販のウォッカより純度が高かったそうだけど何度くらいなのかな? ウォッカは蒸留直後の96%から水を加えて40%程度までと幅広く調整してるから「市販のウォッカより純度が高かった」という情報からでは想像できないですねw |
| …No.542006そうだねx1どの機体だったか失念してしまったのですが、日本陸軍の機体でアルコール燃料でテストしてみたら、異常燃焼を起こして シリンダーヘッドにハチの巣?のように穴が開いてしまい、あやうく墜落するところだったという話を読んだことがあります やはり本来ハイオクタンのガソリン燃料前提で調整されているエンジンでは、アルコール燃料使用は危険だったのでしょうか…? |
| …No.542008+>No.542006 滝沢聖峰の作品でも取り上げてたような |
| …No.542036そうだねx1>やはり本来ハイオクタンのガソリン燃料前提で調整されているエンジンでは、アルコール燃料使用は危険だったのでしょうか…? アルコールはアルミを腐食させる。 詳しくはこちらで。 https://response.jp/article/2001/08/09/10978.html https://www.mlit.go.jp/jidosha/alcohl/alcohl_01.html |
| …No.542037+まあこれでも見よう https://youtu.be/6y8wp5FOEjE |
…No.542039+  >市販のウォッカより純度が高かったそうだけど何度くらいなのかな? >ウォッカは蒸留直後の96%から水を加えて40%程度までと幅広く調整してるから「市販のウォッカより純度が高かった」という情報からでは想像できないですねwポーランドには度数96%の「スピリタス」があるくらいだしまぁ・・・https://nico.ms/sm37970166 |
…No.542046そうだねx3  WW2開戦前、ドイツの航空機会社ハインケル社では、まだ友好国だったノル ウェーに多用途水上双発機He115を輸出していたそうなんですが。出荷の際には先方の希望により、必ず燃料タンクの一つをドイツの蒸留酒シュタインヘーガーでいっぱいにしてのノルウェーまで飛び、引き渡したそうです勿論、He115がこのドイツ製のジンで飛んだというわけではなく、ノルウェーで待ちかねる方々の胃袋に収まったわけですが、タンク一つにおよそ500リットルは入ったというこのシュタインヘーガー、ちゃんと通関手続きとかしたんですかしら(疑) |
…No.542047そうだねx3  因みに、エゲレス空軍の戦闘爆撃機「タイフーン」部隊の指揮官だったデズ モンド・スコット=サンの回想によると、部隊がノルマンディー上陸後フランスに展開した際、支給されるシャンパンに飲み飽きると「イギリス人は自分の国のビールが大好きなので、我々はイギリス本土(略)まで飛ぶ(略)特急便をはじめた」「地元のビール業者が、タイフーンの両翼下の90ガロン落下タンク2本にビールを詰めてくれる(略)パイロットは大急ぎで海峡を越えて(略)戻り(略)ノルマンディーまで飛ぶ間にビールは多少金臭くなるが、隊員たちはかまわず手早く飲み干してしまうのであった」…そうなんですが、「しかし我らの空飛ぶビール馬車が1日に二度もアメリカ軍のサンダーボルトに襲われ、ビールのタンクを海峡に投棄しなければならないことがあったため、この方法も急遽中止になってしまった」 |
…No.542048そうだねx3  「シャンペンと違って、ビールは自腹を切っていたので、この2回の遭遇戦は 高くついた」…んですとかもっとも、「ビールの輸送が途絶えてからは、私は双発のアンソン輸送機でギネスのケースを運ばせるようにした。隊員たちはこれをシャンパンで割ってブラックベルベットを作って飲んでいた。これはとてもロンドン下町っ子の飲み物とはいえなかったが、隊員たちはこれが気に入ったらしく、とりわけセーヌ川を越えて北へ進み、女性の人口の多い地域に入ってからはなおさらだった」…とのことシャンパンとギネス…飲みやすそうですけど、それだけに飲み過ぎて翌朝後悔しそうな組み合わせな気が… |
| …No.542066+盗み飲みもエタノールや地酒のたぐいならまだかわいいもんだけどね メチルアルコールで失明者出す話とか聞くとむしろ正式にアルコール飲料を支給するのが正しいやり方なのかとも思う |
| …No.542067そうだねx2支給されるシャンパンに飽きたってまぁなんと贅沢な話か |
…No.542075そうだねx1  >「しかし我らの空飛ぶビール馬車が1日に二度もアメリカ軍のサンダーボルトに襲われ、ビールのタンクを海峡に投棄しなければならないことがあったため、この方法も急遽中止になってしまった」 ビール輸送は知っていたが、サンボルさん・・・?https://aviationhumor.net/spitfire-bringing-beer-kegs-to-the-men-in-normandy/ちなみに機外懸吊して運ぶと高空の冷気にさらされて到着した時にはキンキンに冷えた美味しいビールになっていたらしい>スピットファイア Mk IX はスピットファイアの進化版であり、翼の下に爆弾や戦車用のパイロンがありました。爆弾のパイロンを改造してビール樽を運ぶこともできることが発見されました。>見つけられる写真によると、さまざまなサイズの樽が使用されていました。緊急時に樽を投棄できるかどうかは不明です。スピットファイアが十分に高く飛んだ場合、高度の冷たい空気がビールをリフレッシュし、到着時にすぐに飲むことができます. |
| …No.542079+基本前線は禁酒のアメリカ軍でも、「薬用」の名目ならウィスキーやブランデーが飲めたそう だから「処方」してくれる軍医が妙に人気者に・・・ |
| …No.542081+そもそも勤務地がドイツやフランスならいくらでも鹵獲して飲めるよね |
| …No.542082+実際現地で酒見つけた連合軍兵士が酒盛り始めて進撃に遅れが出たこともあるはず |
| …No.542084+>航空燃料用にアルコール生産は内地でもやってたね >そして戦後は闇市で売られる怪しげな酒の原料に・・・ メチルアルコールが入ったまま闇で売られたとか。 |
…No.542094そうだねx4  戦艦「大和」の運用科(ダメコン要員)所属だった八代理さんという方の回 想によると、最後の沖縄出撃の際、持ち場で待機していたところに「酒保の倉庫に注水せよ」との命令が来たそうなんですが、「あまりにももったいない」ということで、部下に命じてまず中の酒類を上げさせてからハッチを閉め、注水したそうですwまあ、結局その後「大和」自体が沈んじゃったわけですが一方、こちらは空母「龍驤」乗組みの航空機整備兵だった玉手修司さんの手記にある話なんですが、ソロモン海域の海戦で米空母機の攻撃により、遂に同艦が沈没の憂き目を見た際には、予定されていたトラック島泊地への入港時に飲むつもりでいたビールが、前甲板に山と積まれていたんですとか |
…No.542095そうだねx5  玉手氏曰く 「どうせ沈むならと、だれがいうともなく栓を抜いて飲みはじめた。栓抜きがないので、お手のもののペンチやプライヤーであけて飲んだ。暑さと緊張で、のどがかわききっており、ビールがとてもうまい。酒によわい者は、はやくも桜色になって『矢でも鉄砲でももってこい』といきまきはじめて」…いたそうなんですが、「私が、『爆弾だけはだめだぞ』というと、みなが笑った」…なんて、ややヤケ気味ながら、最後の艦上の宴の場と相成ったそうですまた、おなじく南洋諸島でこちらは南太平洋海戦に参加した、空母「翔鶴」の雷撃機搭乗員だった松田憲雄さんという方は、攻撃後無事傷付いた母艦「翔鶴」に戻ることが出来たそうなんですが、搭乗員待機室に戻ってみると |
…No.542096そうだねx4  「隅の方に不時着糧食が40個ぐらい積んである。今朝の急速発艦で(略)だれ もが飛行機に積んで行かなかったのだ」「われわれの分もあるので、1個取り出し、密封してあるハンダをこじ開けた(略)ウィスキーのポケット瓶1個、牛缶詰め数個、カンメンポウ(略)などが上手に詰め込まれている。『こりゃ、いいや』と3人で牛缶を開け、ウィスキーをチビチビなめ、カンメンポウをかじった」「中村兵曹が『オイ、これじゃものたりん。もう1個あけろ』という。よしと、積んである中から1個取り出して開け、ムシャムシャ、グイグイと調子にのって、次の1個も開けたので、中村兵曹はすっかりご機嫌で、ソファーにひっくり返っていびきをかきはじめた」…そうです命がけの敵空母への雷撃行の疲れに、ウィスキーは覿面だったようなんですが、さてこの非常用ウィスキー、サントリーかニッカか…どこのメーカーの製品だったんですかしら… |
| …No.542131+戦闘機パイロットなんかだと、前線基地の手軽なご褒美が酒類だったりするよね 落とした敵機のエンジンの数だけ一升瓶がもらえたのは日本海軍だったっけ? |
| …No.542136そうだねx1撃墜酒と呼ばれた習慣ですかね? ビルマの航空隊では、たしか撃墜しづらいモスキート偵察機を落とすと日本酒の一升瓶がもらえた、 なんて話を読んだことがあります 海外だとウィスキーとかブランデー、もしくは洒落てシャンパンとかに7なるのでしょうか…(笑 |